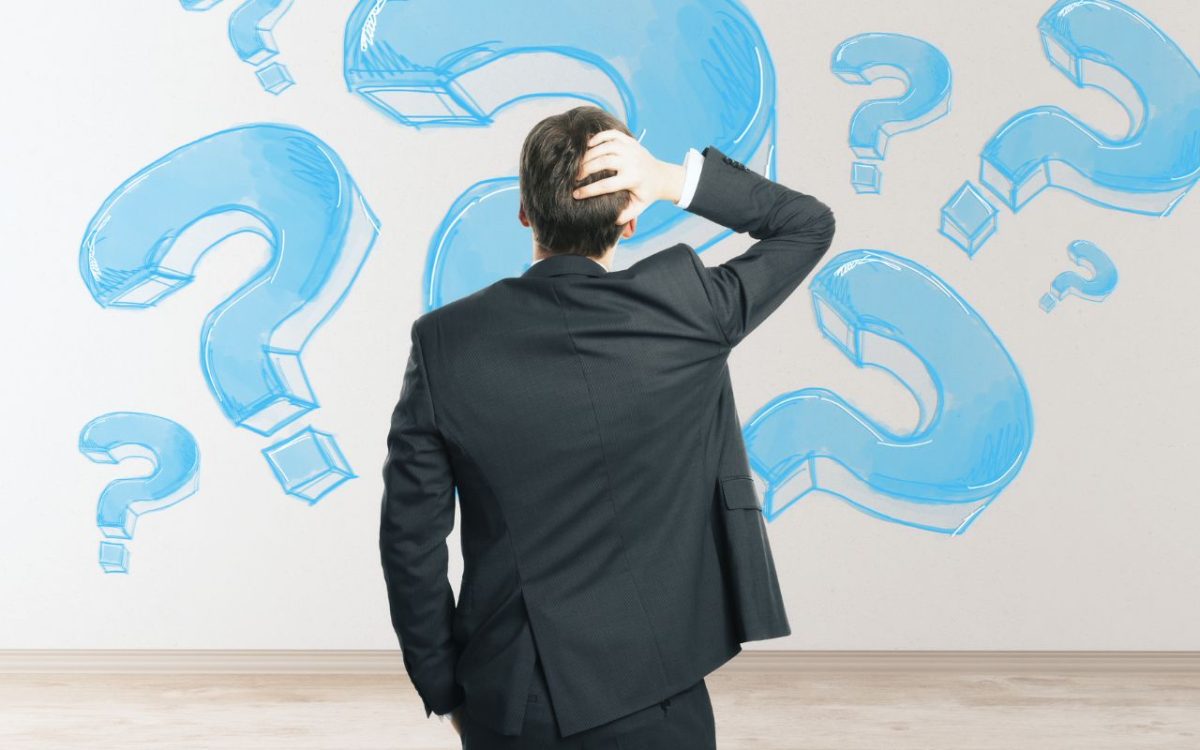
「求人を出しても応募が集まらない」
「ようやく内定を出しても辞退される」
そんな“採用の苦戦”を感じていませんか?求職者の価値観が多様化する今、従来の求人票や面接対応だけでは採用成功につながらなくなっています。
多くの企業が「採用市場の競争激化」や「人材不足」を原因に挙げがちですが、本質的な課題は企業の“内側”にあることが少なくありません。
この記事では、採用がうまくいかない企業に共通する構造的な問題を明らかにし、採用力を高めるために今こそ見直すべき視点として「インナーブランディング」の必要性に触れていきます。
採用がうまくいかない企業には共通する“見えない課題”がある
採用に苦戦している企業では、求人票や媒体の見直しなど表面的な対策だけでなく、組織内部に根本的な課題を抱えていることが多くあります。
ここでは、その代表的な問題を明らかにしていきます。
自社の魅力が候補者に伝わっていない
求人広告や面接の場で自社の魅力をうまく伝えられていないと、候補者の印象に残ることはできません。「働く意味」や「企業のらしさ」が曖昧なままでは、他社との差別化も難しくなり、「どこでもよい」と判断されてしまいます。
採用において重要なのは、スキルマッチよりもカルチャーフィットを意識した情報設計です。自社の価値観や強みを言語化できていない企業ほど、採用において苦戦する傾向があります。
現場と人事の連携が取れていない
人事が主導で採用を進めていても、現場の意向と連動していなければ、的外れな母集団形成や選考が繰り返されます。面接で重視するポイントが不明確だったり、最終判断が曖昧だったりすると、候補者に迷いが伝わり、辞退を招くことにもなります。
現場と人事の連携不足は、採用の質とスピードの両方に悪影響を及ぼすため、組織内での認識共有が不可欠です。
採用の評価基準が属人的になっている
「なんとなく良さそう」「前職が有名企業だから安心」といった印象で判断する採用は、属人化の典型です。評価基準が個人の感覚に依存していると、候補者への対応が一貫せず、社内でも判断の基準がブレてしまいます。
採用における属人性を排除するためには、組織として「どんな人材を採りたいのか」という共通認識と評価軸を定義し、それを共有しておく必要があります。
応募数や内定承諾率だけでは、採用の本質は見えません
採用KPIとしてよく使われるのが、応募数・面接通過率・内定承諾率といった定量的な指標ですが、これだけでは採用の質までは測れません。
特に近年では、候補者が企業を選ぶ基準も多様化しており、数値だけでは把握できない“見えない要因”が採用成功を左右するようになっています。
候補者の離脱理由が分析されていない
「なぜ辞退されたのか」「どのフェーズで離脱されたのか」を把握していない企業は意外と多く存在します。「選考に時間がかかった、説明がわかりづらかった、社風に不安を感じた」これらの要素はすべて企業側がコントロールできる領域です。
数値が低下している原因を“市場のせい”にせず、自社のプロセスや伝え方を振り返る姿勢が求められます。
「選ばれる企業」としての土台が育っていない
採用に苦戦する企業の多くは、「働く理由」や「企業の価値観」をうまく発信できていません。候補者から見たときに、「この会社で働くイメージが湧かない」「どんな人と一緒に働くのか分からない」といった印象を持たれてしまうのは、企業側の自己開示不足が大きな要因です。
“選ばれる企業”になるには、理念や文化をしっかり言語化し、候補者との接点に反映させる工夫が必要です。
採用に必要なのは、仕組みだけでなく“価値観の共有”

ATSや採用管理ツールを導入してフローを整備しても、なぜかうまくいかない。その背景には、組織内で「採用観」がバラバラな状態が潜んでいます。
採用活動を効果的に進めるには、仕組みとあわせて、企業としての価値観・考え方が社内に共有されていることが必要です。
企業文化やビジョンが言語化されていない
理念や価値観が言語化されていなければ、採用の場でそれを伝えることもできません。せっかくの強みがあっても、言葉にできないまま候補者に伝わらず、他社との違いが不明瞭なまま終わってしまうのです。
ビジョンや文化を言葉として整備することで、採用広報の質が一気に向上します。
社内の価値観がバラバラで採用に一貫性がない
面接官によって伝える内容が違ったり、評価ポイントが食い違ったりすると、候補者は「この会社は何を大事にしているのか分からない」と感じてしまいます。これは採用ブランディングの観点でも大きなマイナスです。
全社で「こういう人を採りたい」「こういう文化を守りたい」という軸が共有されていれば、選考全体に一貫性が生まれ、候補者にも信頼感を与えられます。
採用の成果は、社内の意識と仕組みで変えられる
採用がうまくいかないのは、外部環境だけが原因ではありません。むしろ、社内の仕組みや意識のズレが、候補者の離脱やミスマッチにつながっているケースが大半です。これまで述べてきたように、採用の成功には「どんな人を、どんな理由で採りたいのか」という共通認識と、その価値観を伝えられる仕組みが必要です。
そこで今、改めて注目すべきなのが「インナーブランディング」です。インナーブランディングとは、企業の理念やビジョンを社内に浸透させ、社員一人ひとりが自然と“らしさ”を伝えられる状態をつくること。これにより、面接対応や評価の基準、採用広報までもが整合性の取れたものとなり、候補者から“信頼される企業”として認識されやすくなります。
採用に苦戦していると感じるなら、媒体やツールの前に、まずは社内に目を向けてみてください。価値観をそろえ、言葉にする。それが、採用を成功に導く第一歩となるはずです。
【弊社のインナーブランディング事例はこちらをご確認ください。】

深澤 了 Ryo Fukasawa
むすび株式会社 代表取締役
ブランディング・ディレクター/クリエイティブ・ディレクター
2002年早稲田大学商学部卒業後、山梨日日新聞社・山梨放送グループ入社。広告代理店アドブレーン社制作局配属。CMプランナー/コピーライターとしてテレビ・ラジオのCM制作を年間数百本行う。2006年パラドックス・クリエイティブ(現パラドックス)へ転職。企業、商品、採用領域のブランドの基礎固めから、VI、ネーミング、スローガン開発や広告制作まで一気通貫して行う。採用領域だけでこれまで1000社以上に関わる。2015年早稲田大学ビジネススクール修了(MBA)。同年むすび設立。地域ブランディングプロジェクト「まちいく事業」を立ち上げ、山梨県富士川町で開発した「甲州富士川・本菱・純米大吟醸」はロンドン、フランス、ミラノで6度金賞受賞。制作者としての実績はFCC(福岡コピーライターズクラブ)賞、日本BtoB広告賞金賞、山梨広告賞協会賞など。雑誌・書籍掲載、連載多数。著書は「無名✕中小企業でもほしい人材を獲得できる採用ブランディング」(幻冬舎)、「知名度が低くても“光る人材“が集まる 採用ブランディング完全版」(WAVE出版)。「どんな会社でもできるインナーブランディング」(セルバ出版)。「人が集まる中小企業の経営者が実践しているすごい戦略 採用ブランディング」(WAVE出版)

