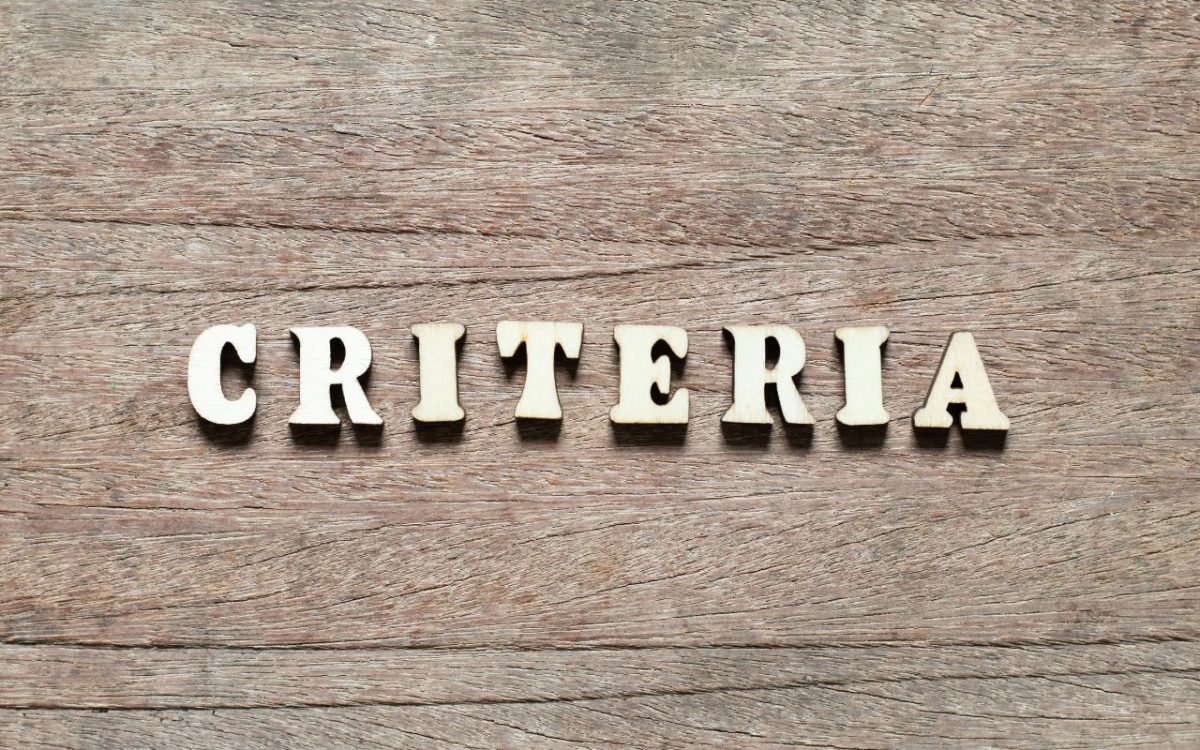
「面接官によって評価がバラバラになる」「どういう人を採るべきか、社内で意見が食い違う」といった採用の混乱は、判断基準が曖昧なことが原因で起きているケースが少なくありません。
明確な採用基準がないまま選考を進めると、採るべき人材を見極められず、内定辞退や入社後のミスマッチにつながるリスクも高まります。
この記事では、採用判断に必要な基準のつくり方と、それを組織に根づかせるために必要なインナーブランディングの視点を解説します。
採用の判断基準があいまいだと、すべてが曖昧になる
判断基準が不明確なままでは、面接・合否判断・求人設計まであらゆる採用活動が曖昧になります。まずは、その影響を具体的に整理しましょう。
面接官ごとに評価基準が異なり、選考結果に一貫性がない
面接官によって「良いと思う人材像」が異なれば、評価ポイントや質問の仕方もばらつきます。その結果、候補者の印象や合否が担当者によって大きく変わることになり、選考の信頼性が損なわれます。
特に複数人で面接を行う場合、基準がバラバラだと合否の判断が感覚的になりやすく、内定を出したものの社内の納得が得られないといった事態も起こりがちです。
属人的な判断が内定辞退やミスマッチを招く
面接官個人の経験や好みに依存した選考は、候補者に「会社としての判断軸がない」と感じさせる原因となります。評価や説明に一貫性がなければ、候補者の不安が増し、結果として内定辞退や早期離職につながるリスクが高まります。
属人化を防ぐには、組織として共通の判断基準を持つことが必要です。
判断基準が言語化されていないと、求人票も曖昧になる
「どんな人を採りたいか」が明確でなければ、求人票に書くべき内容も曖昧になります。
訴求ポイントがぼやけ、ターゲット層に刺さらない内容になってしまえば、そもそも母集団形成もうまくいきません。採用判断の基準が明文化されていれば、求人内容もより具体的で魅力的なものになります。
明確な判断基準をつくるには、組織としての“採用観”が必要
「どんな人を良いとするのか」「何を重視して採るのか」は、企業文化や事業方針と深く関わる部分です。ここでは、組織全体で共有できる判断基準のつくり方を解説します。
価値観とスキルの両面から基準を設計する
採用基準は「何ができるか(スキル)」だけでなく、「どんな考え方で行動できるか(価値観・マインド)」も含めて設計することが重要です。
スキルだけを見て採用しても、カルチャーに合わなければ早期離職の可能性が高まります。採用観に基づいて、両面をバランスよく見られる評価項目を整備しましょう。
現場と人事で“どんな人を採るか”の認識をそろえる
採用判断は現場と人事の連携によって成り立ちます。にもかかわらず、「人事は文化を重視、現場は即戦力重視」といったズレがあると、判断基準が定まりません。
ペルソナを一緒に設計するなど、共通認識を持つ場づくりが必要です。
選考プロセス全体に一貫性が出る
採用観に基づいた明確な基準を持っていれば、選考の各フェーズで判断軸がぶれません。書類選考、一次面接、最終面接と進む中で、「何を見て、どう評価するか」が統一されていれば、選考そのものの質が高まり、候補者への信頼感も生まれます。
判断基準の土台となるのは、インナーブランディング
判断基準を表面上だけで整備しても、それが組織に浸透していなければ形骸化します。基準を支えるのは、「私たちは何を大切にしているか」という価値観の共有です。
“何を良しとするか”の共通認識が組織に根づく
インナーブランディングによって、「この会社はこういう価値観を大切にしている」という共通認識が社内に根づけば、採用判断の拠り所となる“軸”ができます。その軸があることで、誰が選考に関わっても一貫性のある評価ができるようになります。
面接官の育成や採用説明にも一貫性が生まれる
価値観が社内で共有されていれば、新たに面接官を担当する社員へのトレーニングもスムーズに行えます。また、候補者への会社説明や質問の内容にも一貫性が出るため、「話す人によって伝わることが違う」というズレも防げます。
候補者に伝えるメッセージにもズレがなくなる
判断基準が組織に根づいていれば、求人票、説明会、面接、内定後のフォローまで、すべてのフェーズで一貫したメッセージが伝わります。候補者にとっても、「この会社は信頼できる」「自分の価値観と合っている」と感じてもらいやすくなります。
判断の一貫性が、企業の信頼と採用力を高めます
採用判断のブレは、候補者の不信感やミスマッチの原因となります。一方で、基準が明文化され、価値観として社内に浸透している企業では、採用の質もスピードも向上し、結果として「選ばれる企業」になります。
採用活動を仕組みとして改善するなら、まず見るべきは社内の“判断軸”です。インナーブランディングを通じて、採用の軸を定め、それを組織全体に浸透させること。それが、これからの採用力を高める鍵になります。
【弊社のインナーブランディング事例はこちらをご確認ください。】

深澤 了 Ryo Fukasawa
むすび株式会社 代表取締役
ブランディング・ディレクター/クリエイティブ・ディレクター
2002年早稲田大学商学部卒業後、山梨日日新聞社・山梨放送グループ入社。広告代理店アドブレーン社制作局配属。CMプランナー/コピーライターとしてテレビ・ラジオのCM制作を年間数百本行う。2006年パラドックス・クリエイティブ(現パラドックス)へ転職。企業、商品、採用領域のブランドの基礎固めから、VI、ネーミング、スローガン開発や広告制作まで一気通貫して行う。採用領域だけでこれまで1000社以上に関わる。2015年早稲田大学ビジネススクール修了(MBA)。同年むすび設立。地域ブランディングプロジェクト「まちいく事業」を立ち上げ、山梨県富士川町で開発した「甲州富士川・本菱・純米大吟醸」はロンドン、フランス、ミラノで6度金賞受賞。制作者としての実績はFCC(福岡コピーライターズクラブ)賞、日本BtoB広告賞金賞、山梨広告賞協会賞など。雑誌・書籍掲載、連載多数。著書は「無名✕中小企業でもほしい人材を獲得できる採用ブランディング」(幻冬舎)、「知名度が低くても“光る人材“が集まる 採用ブランディング完全版」(WAVE出版)。「どんな会社でもできるインナーブランディング」(セルバ出版)。「人が集まる中小企業の経営者が実践しているすごい戦略 採用ブランディング」(WAVE出版)

